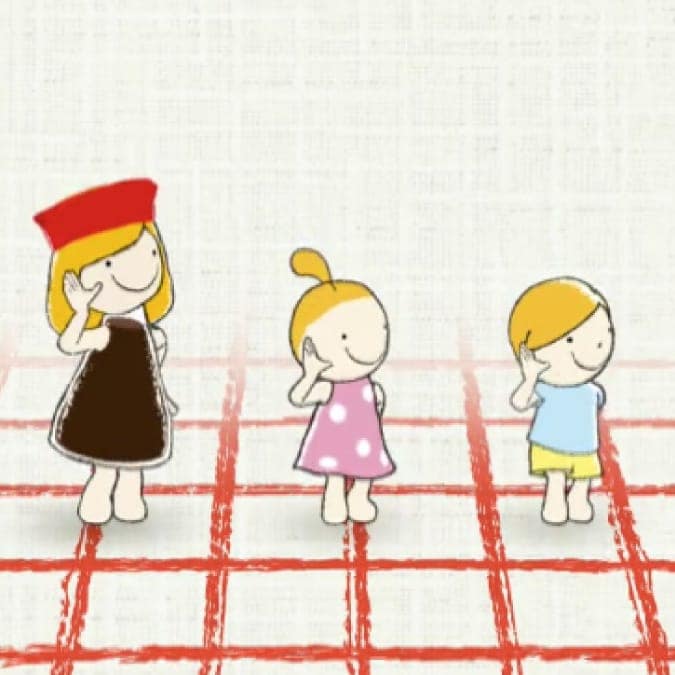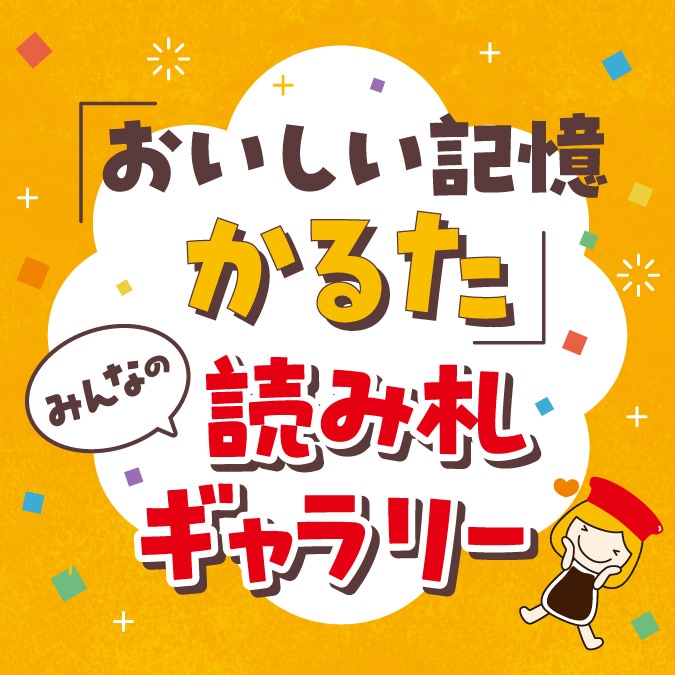Readings
-よみもの-
第16回 一般の部(エッセー)優秀賞
そぼろ丼の味がする日
高校受験を控えていたある日、三者面談で志望校は難しいと言われた。
帰り道、私は感情のやり場がなくて、信号待ちの交差点で言ってしまった。
「わたしのこと、何にも知らないくせに。励ましたりとか、やめてくれない?」
吐き出した瞬間に、取り返しのつかないことを言ったとわかった。
けれど、言葉はもう白い空気の中に放たれていた。
目の前の信号が青に変わるまでの時間が、やたらと長く感じた。
鼻の奥が熱くなって、息が苦しかった。
そんな私に、母は正面を向いたまま、少しだけ口角を上げて言った。
「何年あんたの母親やってると思ってんの」
それきりだった。
振り返らない母の背中を追いかけるように、私も前だけを見て歩き出した。
その一言が胸に染みて、あたたかくて、情けなくて、でも不思議と力が湧いてきた。
その日の夜ご飯は、甘辛そぼろ丼だった。
いつもと変わらない、いや、むしろちょっと濃いめだった。
みりんと砂糖と醤油だけの、なんてことない味付けなのに、しみじみとおいしかった。
味が出尽くすまで、何度も何度も噛んだ。
口の中に広がる甘じょっぱさが、どうしようもなく泣きたい気持ちを、どこかに連れていってくれた。
よくもまあ、これだけでこんなにおいしくなるなと思った。
今日のは、たぶん醤油が多めだった。
社会人になって、今は彼と二人暮らしをしている。
仕事が遅くなった日、
冷蔵庫を開けてひき肉と玉ねぎが目に入ったとき、なんとなくそぼろ丼を作ってみた。
甘辛く炒めた肉の香りが1Lに広がった瞬間、不意にあの日の記憶が蘇ってくる。
彼は「これ、好きだわ」と言って、いつもより早く箸を動かした。
その様子を見ながら、私はなんだか少しだけ泣きそうになった。
母がそぼろ丼に込めてくれた、あのときの気持ち。
それを、今度は私が誰かに渡しているんだと思った。
味は、まだ母には敵わない。
でも、醤油の分量を少しだけ多めにしたのは、あの日の味を思い出してのことだった。
忙しい毎日のなかで、上司に言われた「社交辞令を本気にするな」という言葉が、心に刺さった。
社会って、想像以上にしょっぱすぎる。
誰かの本心がどこにあるのか、探ってばかりいる自分がいる。
そんなとき思い出すのは、あの日のそぼろ丼だ。
あの味だけは、探らなくてもちゃんと伝わる。
あの時の母の気持ちは、口じゃなくて、味に宿っていたんだと今は思う。
うまく言葉にできないとき、人は料理に頼るのかもしれない。
言葉を交わさずとも、伝わるものがあると知ったのは、きっとあの日の夕飯のおかげだ。
INFORMATION
「そぼろ丼の味がする日」
田中 聡子(たなか さとこ)さん(愛知県・27歳)
※年齢は応募時
他の作品を読む
これも好きかも