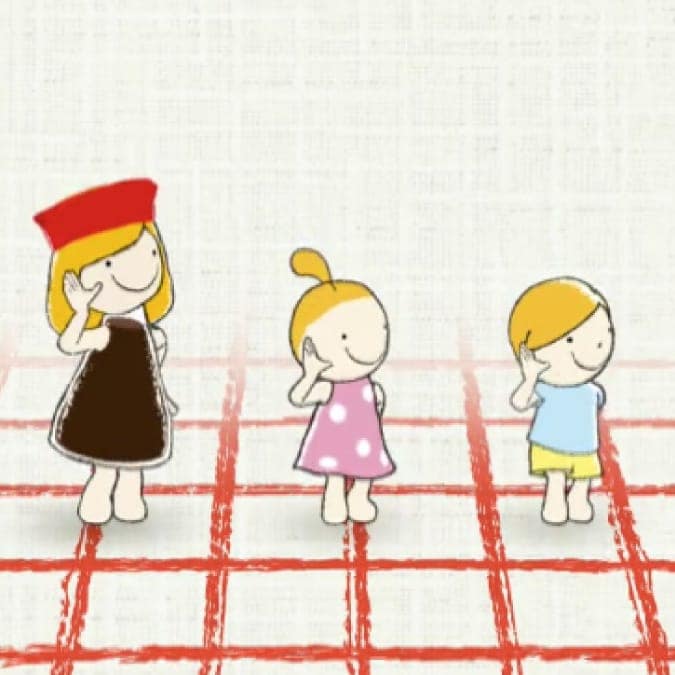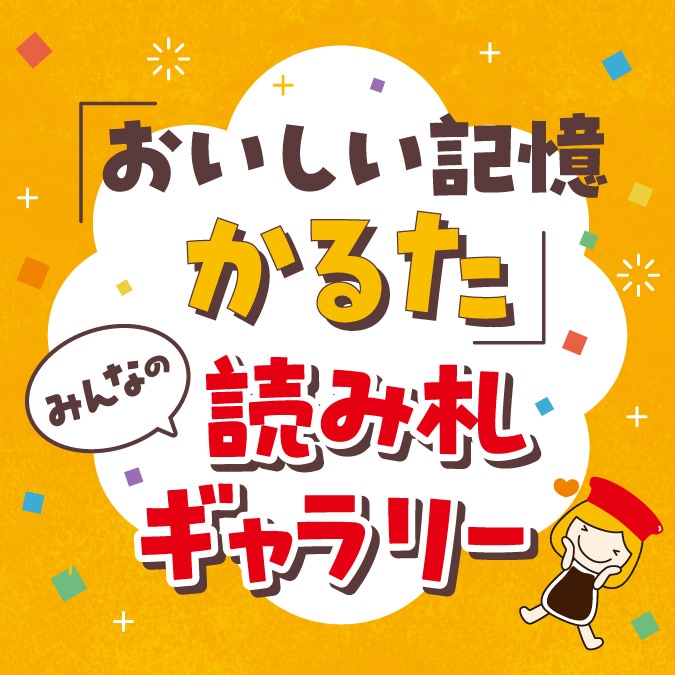Readings
-よみもの-
第4回 読売新聞社賞
ルーもの
彼や夫を繋ぎ止めておくには、胃袋をつかめとよく言うが、その逆だってあると思う。私は何の変哲もない、普通のハヤシライスの味にやられて陥落した。
若い頃の私は忙しかった。母子家庭で育ち、苦労する母を見てきたので、ばりばり働いて自立することばかり考えていた。就職するとすぐ家を出て、平日は夜中まで、ときには休日も働いた。
当時お付き合いしていた彼とは月に数回しか会えず、たまに彼が遊びに来ても、一人放ったらかしにして外出することもあった。それでも一緒にいてくれることが有難い反面、このままではいられないという不安もあった。普通に結婚して落着きたいという彼の気持ちに反して、私は一人の生活を変えようという気がなかった。実家で兄弟の世話や家事をして過ごしてきた日々を思うと、やっと手に入れたマイペースな生活を手放すのが嫌だったのだ。
ある日また私は、遊びにきた彼を部屋に置いて出勤していた。仕事を終えて夕方アパートに戻ると、換気扇から、甘酸っぱい美味しそうな香りが漂ってきている。ドアを開けて目の前のキッチンにあったのは、弱火にかかった鍋だった。
「おかえり。今日の夕飯はハヤシライスよ。」
と、鍋をかき回しながら彼が言う。しばらく使っていなかった炊飯器からは久々に蒸気がたち、鍋の中ではつやつやと光るソースが煮えていた。その香ばしい匂いに、疲れて萎え気味だった食欲が猛烈に刺激された。具は細切れ肉ときのこと玉ねぎという、シンプルなハヤシライスだった。調味料入れの上には、見やすいよう立て掛けたルーの箱が置いてある。料理慣れしていない上にきっちりした性格の彼は、箱に書いてある説明書きを忠実になぞったのだろう。水の分量もしっかり量ってあり、私が普段大雑把に作るものよりずっととろみも強く、味が濃かった。疲れた胃袋に、ちょっと甘く、こってりしたルーが染みとおるようだった。おかわりしてお腹いっぱい食べて、子供にかえったような気分になった。
王道のカレーでもなくハヤシだったのは、辛いものが苦手な私への配慮だった。私の家にはわさびも辛子も置いていない。それならカレーもだめだと、唯一作れる「ルーもの」で、辛くないものを選んだのだという。誰かが自分の好みを考えて材料を揃え、料理してくれたものを帰宅早々食べるなんて、なんという贅沢だろう。一人で作って数日食べ続けるものとは、全く別の食べ物のようだった。
あー美味しかった、と畳にごろりと寝そべると
「どう?二人も悪くないでしょ?たまにはこんな特典もついてくるよ」
と彼が言った。腹におちるとはよく言ったものだ。どんな説得よりもパンチがあった。翌年、私たちは夫婦になった。
10年経った今でも、「ルーもの」は彼の担当だ。几帳面に説明書きに従う彼が作る方が、断然美味しい。教科書どおりの普通の味だが、私にとっては一人でないことの意味を教えてくれた、特別な味だ。
INFORMATION
「ルーもの」
手塚 絵里子さん(東京都・40歳)
※年齢は応募時
他の作品を読む
これも好きかも