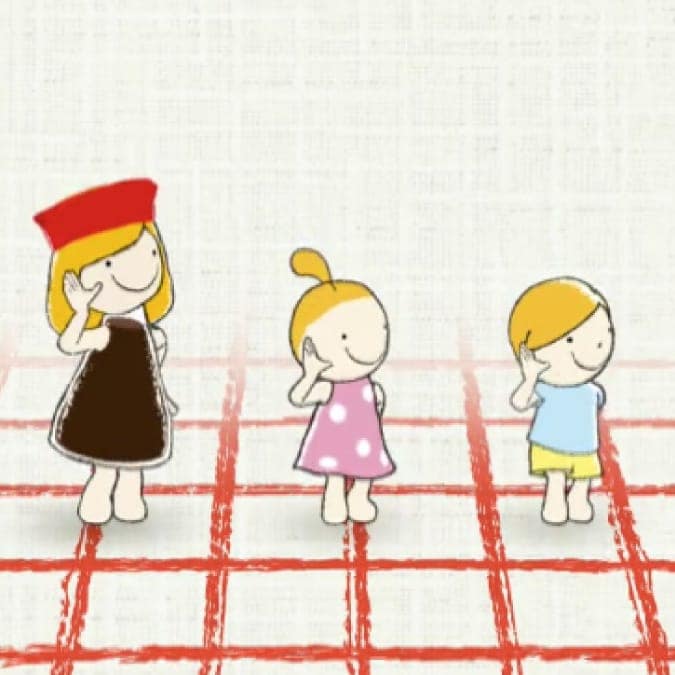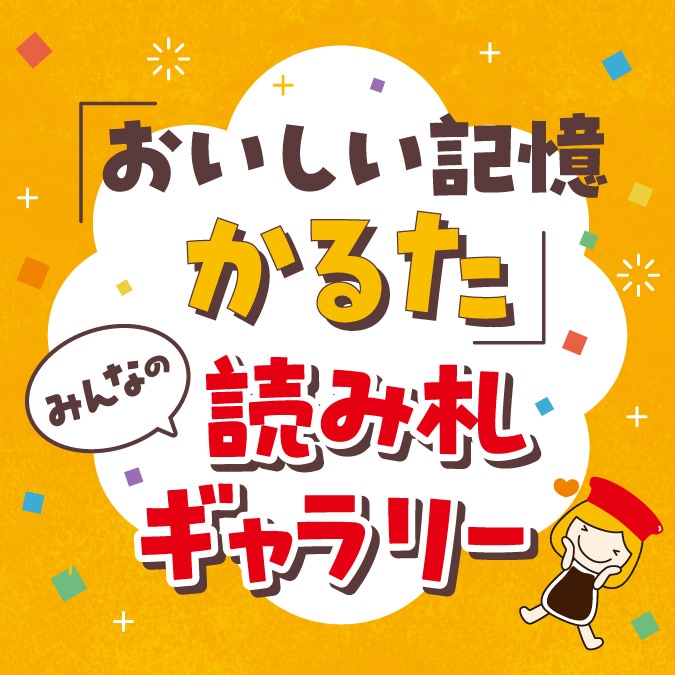Readings
-よみもの-
魔法の一滴【第2回】
初めての米国西海岸単独の添乗は、1972(昭和47年)9月だった。
訪れるのはサンフランシスコ、バンクーバー、ラスベガス、ロサンゼルス、ホノルル。
空港のあらまし。訪問地の観光名所。ホテル周辺の食事場所。
さらにはチップの渡し方と額まで、丸一日かけて特訓を受けた。
出発便は午後四時半の羽田発。当時はまだ成田は開港していなかった。
旅立ちの朝、午前九時に出社したら先輩に手招きされた。
「話は通しておいたから」
上野の弁当業者・ハツネさんに行けという。
いつも団体旅行の弁当調理をお願いしていたが、今回は国内ではなく米国西海岸行きだ。
「行けば分かる」
納得できる理由を先輩から聞かされぬまま、上野に出向いた。
「これを渡すようにと頼まれていますから」
差し出されたのは弁当に添える、魚の形をした容器に詰まった醤油だった。
一個は小さいが、なんと五十個。割り箸が二十膳。
紙袋がぶわっと膨らんでいた。
「受け取ってきましたけど、どうするんですか、こんなモノを」
ふくれっ面で問いかけるわたしを見て、先輩は目元をゆるめた。
「二日目の朝には、これらが役に立つ」
謎めいた言葉を背中に受けて、わたしは羽田から飛び立った。
旅はサンフランシスコ二泊から始まった。
時差の関係で、出発同日の午前中に到着した。
一泊を過ごした翌朝、ホテルで朝飯を摂った。
目玉焼きにカリカリ焼きのベーコンとポテトが添えられていた。
口に広がったベーコンの塩味を、薄いコーヒーで洗い流して喉を滑らせた。
目玉焼きの黄身は大きく、ぷっくりと盛り上がっている。
しかし慣れないフォークでは食べにくいこと、おびただしい。
それでも米国初の朝食を全員で楽しんだ。
翌朝もまた同じ献立である。
「うまそうな目玉焼きだけど、塩で食うのは味気ない」
「こんなとき、醤油があればなあ」
お客様の不満のつぶやきを聞くなり、わたしは部屋へ走った。
そしてあの醤油と割り箸を手にして駆け戻った。
お客様の顔がいきなり明るくなった。
「あんた、若いのに気が利くなあ」
醤油と割り箸で、朝食の雰囲気が劇的に変わった。
若造のわたしは当時二十四だった。
その後は朝食に限らず、食事のたびに魚容器から醤油をひと垂らしした。
そしてナイフ・フォークの代わりに割り箸を使った。
まだ醤油も割り箸も、西海岸では市民権を得られてない時代である。
レストラン・スタッフは不思議そうに客の振舞いを見ていた。
六十三のいまも、目玉焼きには醤油を垂らす。
ひと垂らしが魔法のごとく美味さを引き出してくれた、あの旅の朝が忘れられなくて。
INFORMATION
そのコンテストに寄せて、直木賞作家の山本一力さんが書き下ろしたエッセーをお届けします。
魔法の一滴【第2回】
このエッセーを音声で聴く
他の作品を読む
これも好きかも