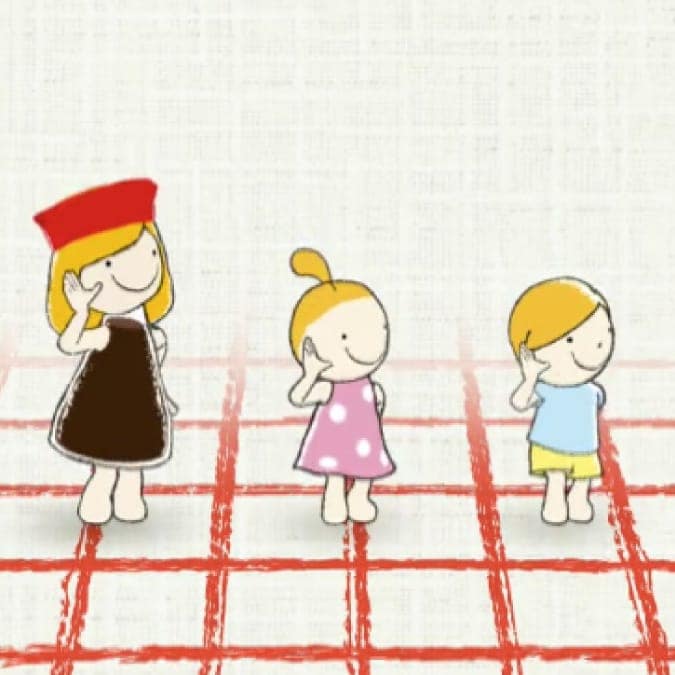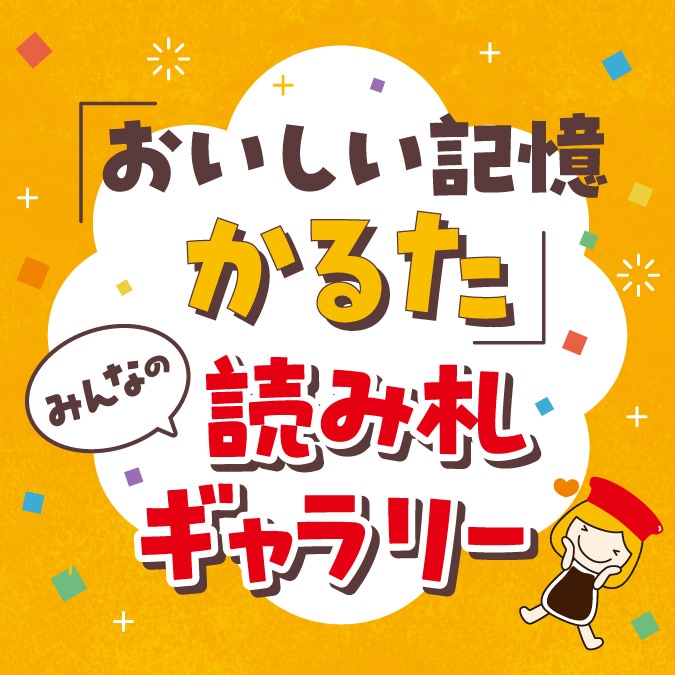Readings
-よみもの-
紅茶と海苔トースト【第11回】
前回の東京五輪は1964年。
あの年、東京の夏は猛烈な渇水にあえいでいた。東京沙漠とまで呼ばれていた。
わたしは当時、都立工業高校2年生。住み込みで、朝夕刊を配達して通学していた。
配達区域の中盤には緑葉を多数の樹木に茂らせた、代々幡斎場があった。
敷地内の木造従業員宿舎も、毎日の配達先だった。
西日を浴びつつの夕刊配達には、斎場の木陰は東京沙漠のオアシスに思えた。
「暑いなか、ご苦労さま」
宿舎のおカミさんは、ねぎらいの言葉とともに、甘い紅茶を振る舞ってくれた。
「冷たいのがいいのは分かってるけど、汲み置きの生水はよくないから」
給水車の水で仕立ててくれた紅茶は、おカミさんの優しさをたっぷり含んでいた。
当時の読売新聞社会面には、毎日の小河内ダム貯水率が報じられていた。
8月下旬に襲来した豪雨を、都民は慈雨だと大喜びした。
大雨でダムは機能を取り戻し、給水制限も段階的に解除された。
斎場のおカミさんは厳しい残暑のなか、水道が生き返ったあとも熱くて甘い紅茶を振る舞ってくれた。
純白の器には、底まで透き通って見える紅茶がお似合いだった。
あの五輪から26年が過ぎた1990年10月10日の祝日。
ロードタイプの自転車で、赤坂の崖下にあった喫茶店を訪れた。
五輪開会式となった10月10日は、晴れの特異日。
高い青空の下、都内をロードで走るのが、毎年この日の楽しみだった。
「きっと食べたことがないトーストだから」
カミさんに従い、崖下に自転車を停めて店に入った。
木造の店内は明るさに乏しかった。が、棚に並んだ白磁のカップの美を、薄暗さが際立たせていた。
トーストは家内に任せたが、飲み物は迷わず紅茶にした。
白いカップを見るなり、 斎場のおカミさんにつながったからだ。
耳もついた5枚切りトーストの真ん中には、海苔がかぶさっていた。
海苔からはみ出した部分は、美味さ約束のキツネ色だ。
スポット照明が、トーストを照らしてくれていた。
添えられた紅茶は懐かしや、カップの底まで透き通って見えていた。
バターが溶け込んだトーストには、醤油が散らされていた。
これが味の決め手だった。
バターの塩味と醤油とは競わず、互いに引き立て合っている。
その旨味を吸い込んだ海苔と、トーストとを同時に頬張るのだ。
呑み込んだあと、口中に留まっている至福感。
極上の塩味を、砂糖を加えた紅茶の甘さが、さらなる高みへと持ち上げてくれた。
あの日以来、 紅茶こそデカフェに変わったが、自宅の朝食は海苔トーストである。
木造宿舎も崖下の喫茶店も失せた。が、紅茶と海苔トーストのおいしい記憶は健在だ。
INFORMATION
そのコンテストに寄せて、直木賞作家の山本一力さんが書き下ろしたエッセーをお届けします。
紅茶と海苔トースト【第11回】
このエッセーを音声で聴く
他の作品を読む
これも好きかも