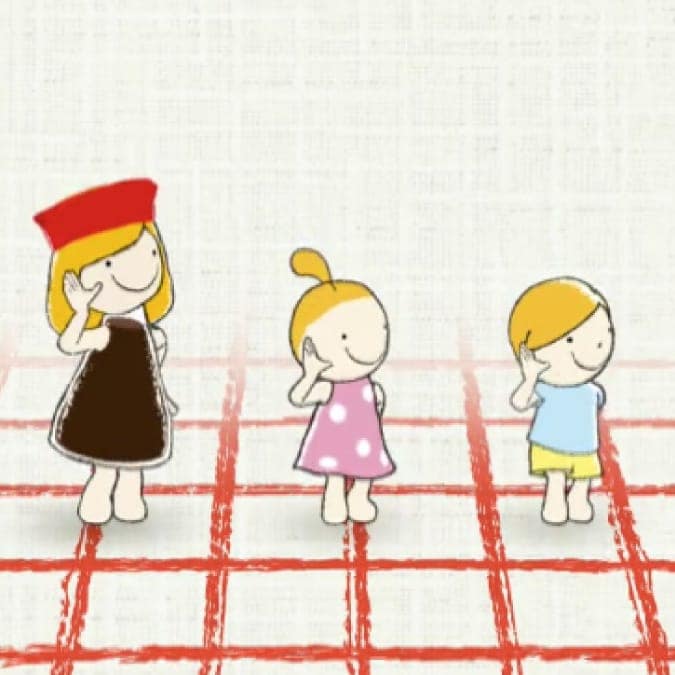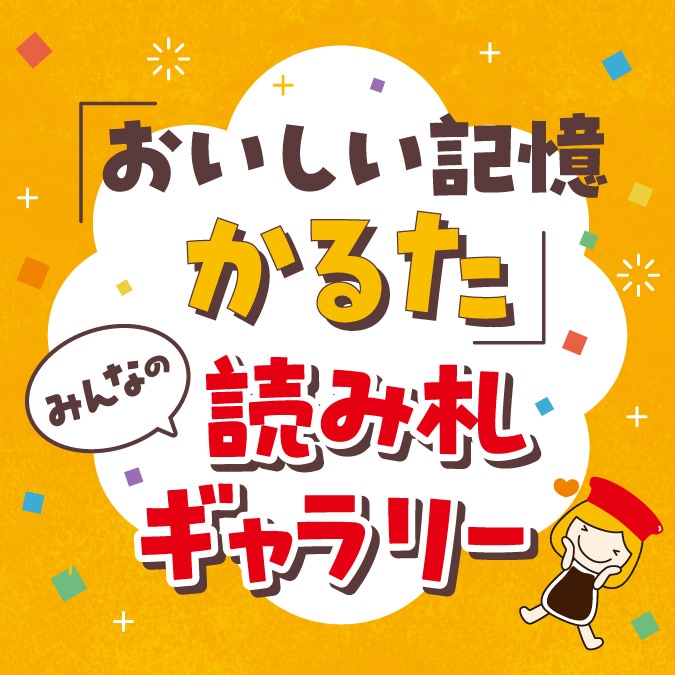Readings
-よみもの-
だから おいしかった……。【第16回】
母は細腕の稼ぎで、妹とわたしを養育してくれていた。限られた休みしかない仕事でも、大晦日と元日は続けて休みが得られた。
31日の母は日の出前から、小学3年の妹を手伝わせて、おせちの煮物作りを始めた。
わたしは六畳ひと間の隅に敷かれた布団のなかで、砂糖と醤油のうまそうなにおいをむさぼり、まだ夜明け前だというのに空腹のおなかを鳴かせていた。
妹を手元に使ってのおせち支度は、昼前に調った。母が番茶で一服していたところに。
仕上がったばかりのおせち料理にも負けない、あのにおいが忍び込んできた。
住まいから200メートル離れた、電車道を渡った先にうなぎ屋があった。店先の焼き台からは行き交う者の足をも止めてしまう、秘伝のたれが焦がされたにおいを、煙が四方に運んでいた。あのときは風向きがよかったのか、住まいにまで流れてきた。
三人同時に風を吸い込み、顔を見合わせた。
「あんたらの手伝いで元日の支度もできたし、お昼はうなぎを食べに行こかねえ」
わたしは土間で、飛び上がって手を叩いた。
焼き台の職人さんとは顔馴染みになるほど、店先で煙は嗅いでいた。が、入るのは初めてだ。母と一緒に入れるのが晴れがましかった。
案内された四人席で、母はうな重を三つと注文した。生まれて初めてのうな重なのに、おとなと同じ一人前を頼んでくれた。嬉しいが、残せないぞと気負い込んだ。
「うなぎは出てくるまで、ひまがかかるきに」
母が言った通りである。店に満ちた蒲焼きの強いにおいを吸い込み、店内を見回した。
かれこれ半時間が過ぎたとき、黒塗り重箱が供された。真っ先にふたを取った。
飴色に焼かれた蒲焼きが、重箱を占領している。箸を付けようとしたら母に止められた。
「こどもでも、蒲焼きには土佐のサンショをかけたほうがええ」
ほどよく振りかけると「食べなさいや」と許しが出た。うなぎを箸で切り割り、口に。
初めてのうな重で、食べ方を知らずだ。うなぎの美味さに搦め捕られたわたしは、うなぎを食べきった。重箱にはたれのかかったごはんだけが残っている。うなぎのあとは、箸でごはんをすくい、口に運んだ。
ごはんに染み込んだたれと、蒲焼きの背が残してくれた旨味。そのごはんも食べ尽くして箸を置き、母を見た。母は半分を残した重箱を、わたしの前に押し出した。
「食べきれんきに、おまえが」と言って。
「今度は蒲焼きとごはんを、一緒に食べなさい。そのほうが美味しいきに」
笑顔の母だったが、いきなり出向くことになったうなぎ屋。さらに翌日にはふたり分のお年玉も控えていた。先行きすべてが不透明のなかで、生きることに懸命な母だったと、我が子を授かって、心底呑み込めた。
後先を案ずるより、子の喜びを大事とした、親の豪気と慈愛。うな重がうまかったわけだ。
INFORMATION
そのコンテストに寄せて、直木賞作家の山本一力さんが書き下ろしたエッセーをお届けします。
だから おいしかった……。【第16回】
他の作品を読む
これも好きかも