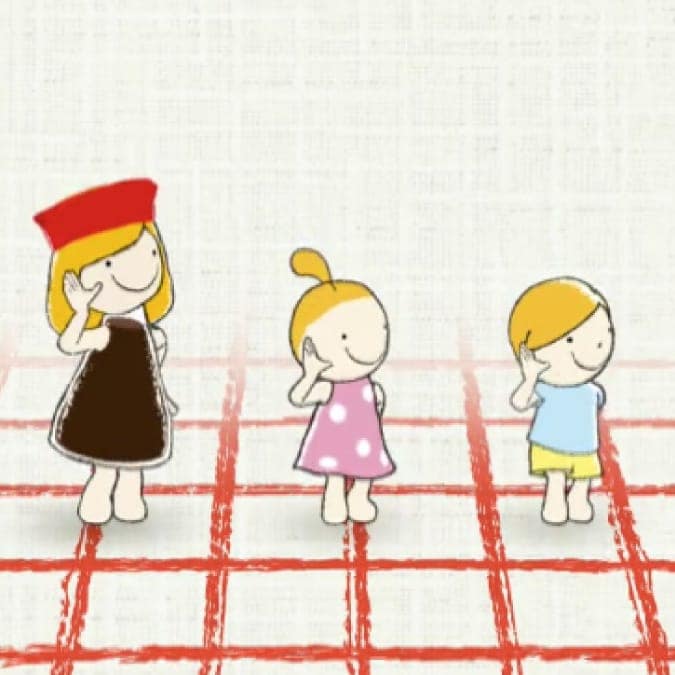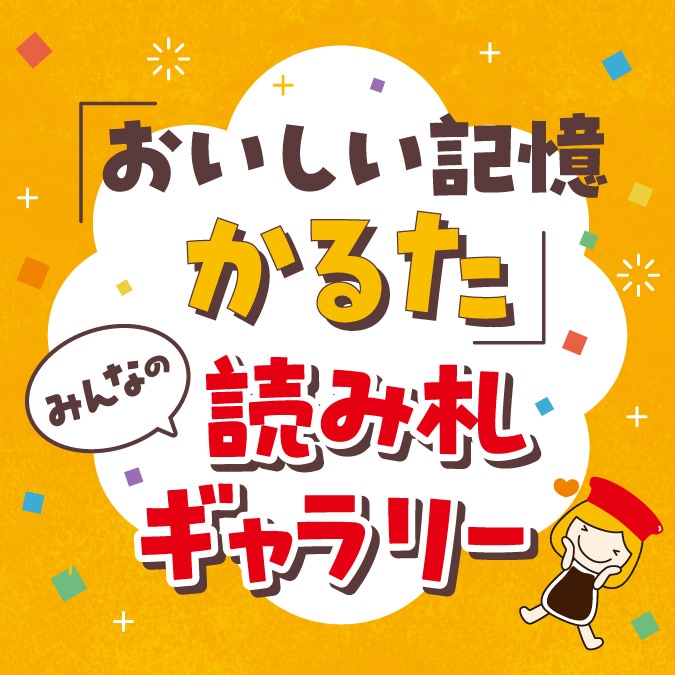Readings
-よみもの-
「焦げた夏」の、ところてん【第17回】
郷里・高知の、中学一年と二年(1960年,1961年)の夏休み。8月1日から30日まで、わたしは氷配達のアルバイトに励んだ。
あの時代の高知で、眩いばかりに白く見えた「電気冷蔵庫」を展示していたのはデパートか繁華街の電気店だったと記憶している。
家庭にあったのは断熱性の高い、焦げ茶色した木製冷蔵庫だ。内に収めて中身を冷やす氷を、半袖シャツと半ズボン姿で毎日配達した。
一貫目(3・75キロ)の横長の氷を、配達先台所の土間などで半分に切り分け、二個を冷蔵庫に収めるまでが仕事である。
氷を切り分けたあとは、まな板に飛び散った氷クズを、持参した鉄コップに集めた。
配達自転車にまたがる前、溶けた氷クズを呑み干した。冷たいだけの水が、夏日で焦がされた身には、なんとも美味かった。
配達の仕舞いは「おばやん」と呼んでいた、店主のおとみさんがひとりで商う駄菓子屋である。納めるのは四貫。冷蔵庫は大型だが、商いで使うかき氷機は五百匁しか乗らない。八個に切り分けて納めた。
飛び散った氷クズもアルミのボウルに集めて冷蔵庫に。
これで午前中の仕事は終わりだ。空腹をところてんで満たすのが、毎日の楽しい決まりだった。
バイト代は朝9時~午後4時までで日当50円。そのなかから10円を、一杯5円のところてん二杯分に遣った。おばやんは二杯をまとめて、どんぶりで拵えてくれた。
当時の高知のところてんはだし汁で食べた。鰺だしの濃い汁は、どんぶりの底が透けて見えるほどに澄んでいた。
おばやんはどんぶりの真上で、二個分をひと息で突いた。てんぐさたっぶりのところてんは澄き通った黒色だ。汁と混ざり合っても、はっきりと見えた。
仕上げはショウガ。おろし金ですりおろされた土佐名産のショウガは香りも高く、黄色がところてんの上で輝いているかに思えた。
「もう、食べてもええきに」
おばやんのゆるんだ目元を見るなり、両手でどんぶりを抱え持った。そしてショウガと汁とを混ぜ合わせた。
澄んでいても鰺だしと醤油は味が濃い。しかしショウガも負けていない。汁の美味さを喉に流してから、どんぶりを卓に戻した。そして一気にところてんを味わった。
夏日を浴びながら氷運びを続けた身体に、ところてんと汁とが染み渡った。
一杯5円のところてんを、二杯も食べられたのだ。存分に働いてくれた身体への、なによりのご褒美だった。
あれから六十余年が過ぎた、2026年厳冬の元日。こたつに足を入れて、ところてんを賞味した。
汁はカミさんが仕上げた鰺だしだ。
「真夏やのうたち、真冬もうまいきに」
不意に思い出したおばやんの言葉で高知のあの夏を、こたつに差し入れた足が感じ取っていた。
INFORMATION
そのコンテストに寄せて、直木賞作家の山本一力さんが書き下ろしたエッセーをお届けします。
「焦げた夏」の、ところてん【第17回】
他の作品を読む
これも好きかも