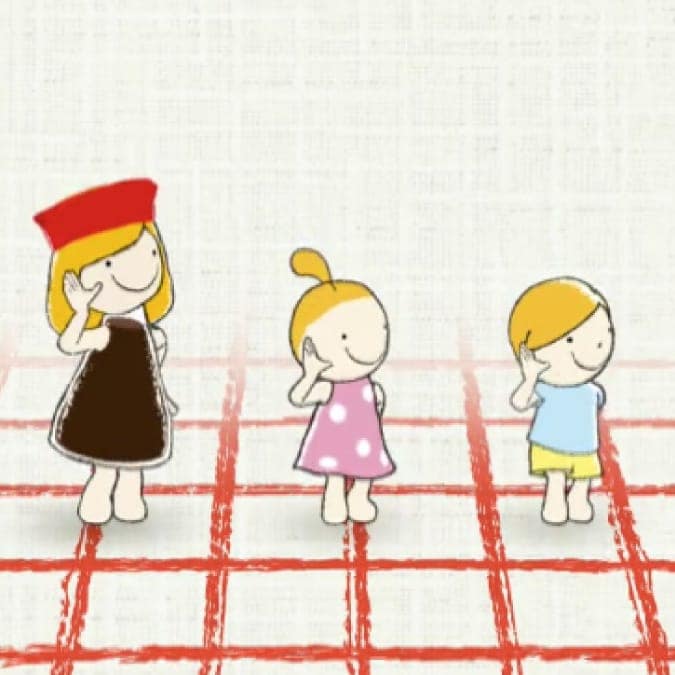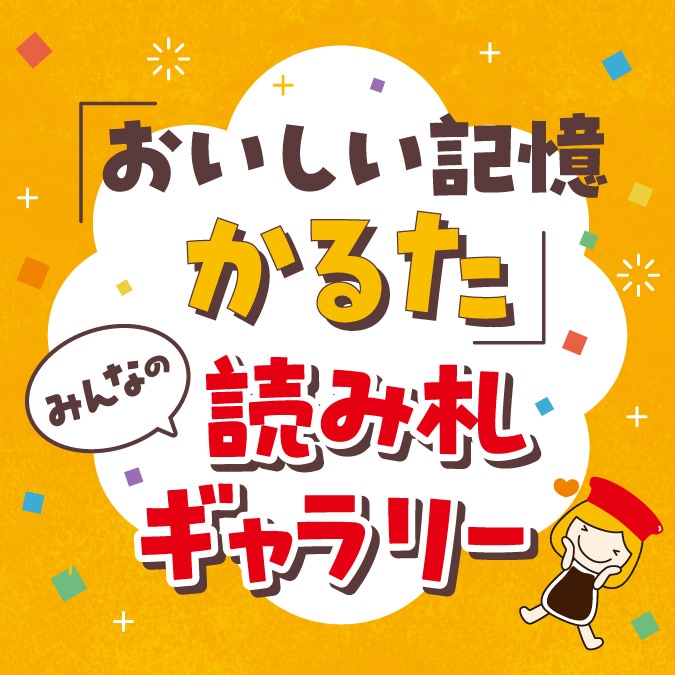Readings
-よみもの-
駅前食堂のピーナッツ味噌【第8回】
昭和42(1967)年1月、国鉄(当時)上野駅から石打駅まで、スキー列車に添乗した。
スキーバスが全盛期を迎える前だ。
石打到着は早朝5時。
駅前の提携食堂で朝食休憩のあと、スキー客は夜明け直後のゲレンデに向かった。
出払ったあとが添乗員の食事だ。朝食膳の小鉢を見て、思わず声を挙げた。
「あっ……ピーナッツ味噌だ」と。
「あらまあ。あんた、これを知ってるかね」
食堂のおかみさんが驚き顔になった。
「新聞配達当時、週に一度は食べてました」
「あんた、東京のひとだよねえ?」
スキー客が食べ終えた膳の片付けを止めて、おかみさんはわたしの前に座り込んだ。
母と妹が働いていた読売新聞富ヶ谷専売店に、わたしも一年遅れで住み込んだ。
そして朝夕刊を配達しながら、渋谷区立上原中学に通い始めた。
朝刊配達を終えた5日目の朝。
得体の知れないおかずが小鉢で供された。
「ピーナッツ味噌ぞね」
賄い婦で住み込んでいた母の返事である。
ごはんは巨大な電気釜のなかで、お代わり自由だ。
味噌汁も大鍋にたっぷり残っていた。
おかずは日替わりで一品。
ピーナッツ味噌は、わたしにはこの朝が初だった。
味噌に包まれたピーナッツを口に運んだ。
味噌は甘いし落花生は硬い。
配達後で空腹の極みだったが、二箸目をつける気にはならなかった。
他におかずはない。
仏頂面で味噌汁をごはんにかけていたら、母に戒められた。
「ご他人様の釜の飯を食べるときは、好きやら嫌いやら言うたらいかん。慣れなさい」
長野県出身の店主ご夫妻には馴染みの郷土料理だった。
しかし油で炒めたピーナッツを味噌と砂糖で仕上げた味は、高知では食べたことなどなかった。
調理を言いつけられた母も、最初は戸惑ったらしい。が、すでにすっかり調理を会得していた。
その後も週に一度は朝食に出された。
朝刊配達で存分に走ったあとでは、味噌とピーナッツの甘味を、好ましくすら思い始めていた。
「都会のひとには受けないと言っても、うちのひとは聞かないから……」
おかみさんが片付けている朝食膳には、手つかずのピーナッツ味噌小鉢が幾つもあった。
夜行列車下車直後の起き抜けでは、硬いピーナッツなど食べる気にはならないのだろう。
「滑ったあとの昼飯に出したらどうですか」
朝夕刊配達の経験から提案したら、店主は納得したらしい。
朝定食を食べ終えたばかりなのに、熱々のうどんをサービスされた。
新聞配達の日々は、すでに半世紀以上もの彼方である。
毎日の暮らしの料理が多彩になったら、好き嫌いを言うことが多くなった。
そんなおのれを戒めるには、ピーナッツ味噌は良薬かもしれない。
INFORMATION
そのコンテストに寄せて、直木賞作家の山本一力さんが書き下ろしたエッセーをお届けします。
駅前食堂のピーナッツ味噌【第8回】
このエッセーを音声で聴く
他の作品を読む
これも好きかも